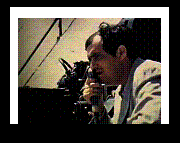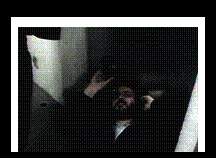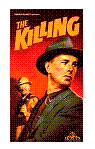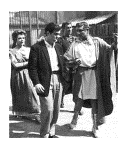<Chapter2 Filmography>
作品
『恐怖と欲望』 (1953/Fear and Desire)
残念ながら、この作品はキューブリックの意向により封印されたままである。
『非情の罠』 (1955/Kille's Kiss)
この作品は、キューブリックにとって初めてのオールロケ撮影作品で陰影のあるシーンが印象的だ。
『現金に体を張れ』(1956/The Killing)
この作品は、キューブリックのメジャーデビューと言っていい映画である。原作はライオネル・ホワイト「逃走と死と」である。 僕にとっては、永く幻の作品となっていたが、5年前ぐらいだろうか、初めて観たのが「WOWOW」での放送だった。まず、脚本が非常に優れていて、一級の娯楽作品として見応えのあるところに惹かれた。同じ目的に辿りつくまでの、それぞれの登場人物がどのような行動をしたのか、時間を後戻りさせ同時進行していく表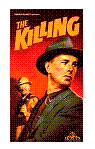 現手法は驚きに値する。この手法はのちにタランティーノが「レザボアドッグズ」で真似ていることはつとに有名だ。主役のスターリング・ヘイドンはアメリカ映画のタフガイを代表する、骨太な知能犯を演じているが、男からみてもこの役者には魅力を感じる。特に人を殺さずに競馬売上金を強奪しようとする計画は、実際の場でも十分通用しそうなリアリティがあった。B級の犯罪アクションものに思われがちだが、緻密な構成と中年俳優たちの個性が生かされており、一級の犯罪サスペンス映画と言ってよい。レース中の馬を射殺するために雇われたスナイパー役の俳優は、どこかニコラス・ケイジに風貌が似ていて好きになってしまった。ラストのあっと言わせる展開には、どことなく不条理さとともに爽快感と潔さがあって、印象深いものになっている。キューブリックとジェームズ・ハリスはこの映画でついにメジャー進出は実現することになる。 現手法は驚きに値する。この手法はのちにタランティーノが「レザボアドッグズ」で真似ていることはつとに有名だ。主役のスターリング・ヘイドンはアメリカ映画のタフガイを代表する、骨太な知能犯を演じているが、男からみてもこの役者には魅力を感じる。特に人を殺さずに競馬売上金を強奪しようとする計画は、実際の場でも十分通用しそうなリアリティがあった。B級の犯罪アクションものに思われがちだが、緻密な構成と中年俳優たちの個性が生かされており、一級の犯罪サスペンス映画と言ってよい。レース中の馬を射殺するために雇われたスナイパー役の俳優は、どこかニコラス・ケイジに風貌が似ていて好きになってしまった。ラストのあっと言わせる展開には、どことなく不条理さとともに爽快感と潔さがあって、印象深いものになっている。キューブリックとジェームズ・ハリスはこの映画でついにメジャー進出は実現することになる。
『突撃』(1957/Paths of Glory)
原作は、ハンフリー・コッブの反戦小説「栄光への小経」である。この本を少年時代にキューブリックは読んでいたらしい。主演はカーク・ダグラスで撮影はすべてドイツで行っている。この映画の内容は、フランス軍部の腐敗を痛烈に批判したものであるため、本国フランスでは未だに上映禁止となっている。主演には「ス パルタカス」で一緒に仕事をすることになるカーク・ダグラスで、当時にビッグスターを起用することは、映画会社から資本を引き出すうえで、さすがのキューブリックも承諾せざるを得なかったと推測できる。1957年の製作当時、キューブリックはこの作品を本当のメジャーへの挑戦と考えていたに違いない。長年この作品を観たいと思っていたが、ビデオもリリースされておらず、念願がかなったのはつい最近のことである。まず、驚かされたのは移動撮影の見事さである。爆音や銃音が鳴り響く塹壕をカーク・ダグラスが歩くシーンで、手ブレのない流麗なカメラワークはキューブリックの真骨頂だ。「時計じかけのオレンジ」で撮影監督だったジョン・オルコットはこう述べている「彼のように手持ちカメラを揺らさずに撮影できる人をいままで会ったことがない。」まるで、「突撃」の移動撮影はまるでステディカムで撮ったようなほど安定感がある。 パルタカス」で一緒に仕事をすることになるカーク・ダグラスで、当時にビッグスターを起用することは、映画会社から資本を引き出すうえで、さすがのキューブリックも承諾せざるを得なかったと推測できる。1957年の製作当時、キューブリックはこの作品を本当のメジャーへの挑戦と考えていたに違いない。長年この作品を観たいと思っていたが、ビデオもリリースされておらず、念願がかなったのはつい最近のことである。まず、驚かされたのは移動撮影の見事さである。爆音や銃音が鳴り響く塹壕をカーク・ダグラスが歩くシーンで、手ブレのない流麗なカメラワークはキューブリックの真骨頂だ。「時計じかけのオレンジ」で撮影監督だったジョン・オルコットはこう述べている「彼のように手持ちカメラを揺らさずに撮影できる人をいままで会ったことがない。」まるで、「突撃」の移動撮影はまるでステディカムで撮ったようなほど安定感がある。
また不条理な軍隊の性質を鋭く浮かび上がらせ、処刑の場面ではそのやるせない感情が爆発しそうになる。キューブリックが最も造詣が深いのは軍隊という組織であり、人間の愚かさが極端に現われやすい存在なのかもしれない。 なお、この映画のラストに登場する酒場の踊り子は、キューブリックが死ぬまで添い遂げた、3度目の妻スザンヌ・クリスチャンである。
『スパルタカス』(1960/Spartacus)
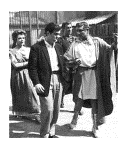 「ジョニーは戦場へ行った」の脚本家ダルトン・トランボと当時の大スターカーク・ダグラスの映画といっていいほど、キューブリックが辛酸を舐めた作品である。歴史ドラマとしてオーソドックスなつくりは否定できないが、場面場面では、いかにもキューブリックらしい演出を見出すことができる。 当初予定した監督アンソニー・マンがカーク・ダグラスと衝突したため即刻クビになり、代役を探していたところ「突撃」で一緒に仕事をしたキューブリックをカークが指名し、引き継いで監督をしたというのが真相である。若干31歳のキューブリックはこの映画を何とか自分の映画にしようと試みたが、ハリウッドのがんじがらめのシステムには勝てず、渋々演出したらしい。ことごとく演出に口出しするダグラスは、俺の映画だという意識が強く、結果的には興行で大成功を収めたのだが、理論的に練りに練った演出をするキューブリックを嫌い、お互いそれ以後は一切の関係を断ち切っている。キューブリックも、この作品は自分のフィルモグラフィーとして認めていない。 「ジョニーは戦場へ行った」の脚本家ダルトン・トランボと当時の大スターカーク・ダグラスの映画といっていいほど、キューブリックが辛酸を舐めた作品である。歴史ドラマとしてオーソドックスなつくりは否定できないが、場面場面では、いかにもキューブリックらしい演出を見出すことができる。 当初予定した監督アンソニー・マンがカーク・ダグラスと衝突したため即刻クビになり、代役を探していたところ「突撃」で一緒に仕事をしたキューブリックをカークが指名し、引き継いで監督をしたというのが真相である。若干31歳のキューブリックはこの映画を何とか自分の映画にしようと試みたが、ハリウッドのがんじがらめのシステムには勝てず、渋々演出したらしい。ことごとく演出に口出しするダグラスは、俺の映画だという意識が強く、結果的には興行で大成功を収めたのだが、理論的に練りに練った演出をするキューブリックを嫌い、お互いそれ以後は一切の関係を断ち切っている。キューブリックも、この作品は自分のフィルモグラフィーとして認めていない。
のちにカーク・ダグラスは自伝の本でキューブリックをこう評している「あいつは、才能あるクソったれだ!」と。
『ロリータ』(1962/Lolita)
 旧ソ連からアメリカへ亡命した作家、ウラジミール・ナボコフが、アメリカのカウンターカルチャーを素直に感じた思いを込め 旧ソ連からアメリカへ亡命した作家、ウラジミール・ナボコフが、アメリカのカウンターカルチャーを素直に感じた思いを込め
て執筆したのが小説「ロリータ」である。この原作を映画化する権利をキューブリックとハリスは早い時期から取得していた。「ロリータ」は、そのスキャンダラスな内容のため、検閲団体やカソリック団体からの抗議は必至であった。そのため、検閲には比較的緩やかで、製作費面でもハリウッドよりコストがかからないイギリスで撮影することにした。その後、キューブリックは英国を拠点として映画製作をすることになり、言わば、英国にいながらアメリカ映画をつくり続けた希有な人物として注目された。
作品としては、少女に惑わされる中年男の姿が妙に滑稽に見えて、セクシャルな部分よりも、やや人間の愚かさがブラックユーモアたっぷりに描かれいる。特に過激な描写はなく暗示の部分も多いが、J・メイスンの映画というよりも、やはりキルティを演じるP・セラーズの映画のような見方もできる。この映画は、キューブリックにとって初の興行的にヒット作として、語り継がれることになる。
『博士の異常な愛情』
(1964/Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop
Worrying and Love the Bomb)
撮影しているうちに、核戦争の恐怖を描いた作品がシリアスにしようとすればするほど、逆にコメディに近い内容になってい
ったのに気づいたキューブリックは、最終的にブラックコメディとして完成させる判断を下した。当時は冷戦時代の真っ只中で、キューバ危機などはまさに現実の恐怖としてアメリカ国民を震撼させた出来事だった。
 この映画がキューブリック最高傑作であるとの声も多いが、それは、ブラックコメディをこれほど芸術作品としてもレベルの高い映画に昇華させた結果に対しての賞賛だと言える。この映画に登場する人物はすべてどこか狂っているように描かれている。核兵器の命令を下す将軍は、「ソ連が飲料水に毒を入れた」と被害妄想にとりつかれる。戦闘機のパイロットは任務遂行のためにひたすら低空飛行を続ける。命令に対してまったく疑いももたずに。ストレンジラブ博士は放射能が低レベルになるまでは100年はかかるだろうが、男1人に女10人の割合で地下壕で生活することで、人類は生き延びることができるだろうと奇想天外な提案する。そして延々と繰り返されるキノコ雲のショットに「また会いましょう」の歌が重なるエンディング。これ以上の皮肉はないと言えるほど、ブラックユーモアの極致だ。 同じようなモチーフで同時期にシドニー・ルメットが「未知への飛行」を製作している。こちらのほうは、硬派な内容で原作に忠実につくられているのだが、キューブリックは脚本家のテリー・サザーンと共同執筆し、核の恐怖を描こうと思えば思うほど、どこかコミック的な内容になりがちになることに気が付き、思い切って「ブラックユーモア」で全編を通すことにしたのだった。「人間なんて本当に愚かな生き物さ」とでもいわんばかりのこの作品は、興行的に大ヒットを放ち一躍キューブリックは名声を得ることになる。 この映画がキューブリック最高傑作であるとの声も多いが、それは、ブラックコメディをこれほど芸術作品としてもレベルの高い映画に昇華させた結果に対しての賞賛だと言える。この映画に登場する人物はすべてどこか狂っているように描かれている。核兵器の命令を下す将軍は、「ソ連が飲料水に毒を入れた」と被害妄想にとりつかれる。戦闘機のパイロットは任務遂行のためにひたすら低空飛行を続ける。命令に対してまったく疑いももたずに。ストレンジラブ博士は放射能が低レベルになるまでは100年はかかるだろうが、男1人に女10人の割合で地下壕で生活することで、人類は生き延びることができるだろうと奇想天外な提案する。そして延々と繰り返されるキノコ雲のショットに「また会いましょう」の歌が重なるエンディング。これ以上の皮肉はないと言えるほど、ブラックユーモアの極致だ。 同じようなモチーフで同時期にシドニー・ルメットが「未知への飛行」を製作している。こちらのほうは、硬派な内容で原作に忠実につくられているのだが、キューブリックは脚本家のテリー・サザーンと共同執筆し、核の恐怖を描こうと思えば思うほど、どこかコミック的な内容になりがちになることに気が付き、思い切って「ブラックユーモア」で全編を通すことにしたのだった。「人間なんて本当に愚かな生き物さ」とでもいわんばかりのこの作品は、興行的に大ヒットを放ち一躍キューブリックは名声を得ることになる。
『2001年宇宙の旅』(1968/2001: A Space Odyssey)
映画の歴史に燦然と輝く金字塔が、この傑作である。どれだけこの作品が、それ以降の映画に対し、技術とイメージの影響を与えたかは言うに及ばずである。この映画を観た少年たちが、内容はよくわからずとも、圧倒的なリアリティに打ちのめされ、映画をつくりたいという夢を持たせたほど、作品のもつ強大なパワーは誰でも認めざるを得ないだろう。
そのキューブリックの申し子が、いわゆるハリウッドのヒットメーカーとして現在成功している、マーティン・スコセッシ、S・スピルバーグ、J・キャメロン、G・ルーカス、L・ベッソン、ヤン・デ・ボン、J・マクティアナンたちである。この映画は、難解であったため批評家からは、敬遠されたが、一部の若者には熱狂的に指示された。
この映画のヒットにより、メジャー会社も出資をするようになり次回作とし て、当時は一般的なSF作家だったアーサー・C・クラークの短編小説「前哨」をモチーフにした映画を製作すると発表した。 まず、クラーク本人にコンタクトを取り、共同で脚本を執筆することになった。それが名作「2001年宇宙の旅」である。製作資金はMGMが出資することになり、イギリスで撮影が開始された。 製作にあたっては、当時の最高のスタッフが集められ、技術の結晶によるSF最高傑作が誕生することになる。キューブリックは当初、カール・セーガンのナレーションを入れ、ところどころにボイスオーバーで説明をすることを考えていた。しかし、言葉やナレーションで説明するよりも、映像のみで観客のイメージに訴えることが効果的であると判断し、一切の説明部分を削除した。そして、音楽も映画音楽を作曲者に依頼していたものを、既製のクラシック音楽と呼吸音のみで通すことに決め、作曲家アレックス・ノースが裁判に訴える事件も起 て、当時は一般的なSF作家だったアーサー・C・クラークの短編小説「前哨」をモチーフにした映画を製作すると発表した。 まず、クラーク本人にコンタクトを取り、共同で脚本を執筆することになった。それが名作「2001年宇宙の旅」である。製作資金はMGMが出資することになり、イギリスで撮影が開始された。 製作にあたっては、当時の最高のスタッフが集められ、技術の結晶によるSF最高傑作が誕生することになる。キューブリックは当初、カール・セーガンのナレーションを入れ、ところどころにボイスオーバーで説明をすることを考えていた。しかし、言葉やナレーションで説明するよりも、映像のみで観客のイメージに訴えることが効果的であると判断し、一切の説明部分を削除した。そして、音楽も映画音楽を作曲者に依頼していたものを、既製のクラシック音楽と呼吸音のみで通すことに決め、作曲家アレックス・ノースが裁判に訴える事件も起
きている。しかし、幾多の困難を乗り越え、ついにキューブリックはこの作品を仕上げ、MGMに巨額の収益を与えることになった。リアリティを追求することで、映像にはその労力を惜しまず注いだことは言うまでもない。特に、科学的に裏付けされたものを徹底的に追求し、それを未来の姿として描いてみせた。例を挙げれば、宇宙は真空なので、まったく音がしない静寂につつまれているため、当然宇宙船も無音なわけで、その後「スター・ウォーズ」などからは、リアリティよりもファンタジックやアクション部分に焦点をあてた映画が主流となった。船の爆音など、冒険活劇を重要とするサウンドが常識となったが、映像、サウンドにおいてデジタルの最盛期を迎えた現在に至っても、この作品を越えるほどの質の高い作品は、未だに現れてはいない。
キューブリックは、「アイズ・ワイド・シャット」の撮影後に、現在の最高のデジタル技術を使って、「スター・ウォーズ」を越えるような内容で、かつ社会的な映画としての質を落とさないSF映画を製作することに意欲を燃やしていた。それが未完のSF大作「A.I」になるはずだった。
『時計じかけのオレンジ』(1971/A Clockwork Orange)
 この映画は、僕にとって映画の歴史上で、金字塔といえるくらい重要な映画だ。その過激すぎる内容は、暴力やセックスの場面が登場するため、一部批評家や観客からは毛嫌いされている傾向もあるが、それは「木をみて森を見ず」と同じことではないかと考えている。この映画の本質は、「体制主義による管理の脅威」にあることを読み取る必要がある。人間の本能というべき欲望を抑えるために、その人間を社会が人工的に洗脳し管理した場合、行き着くところはどうなるかという重要なテーマが隠されている。しかし、公開当時にイギリスの世論はキューブリックに厳しく、暴力を肯定する危険な人物と一方的に弾劾され、不穏な社会状況と相まみれてか、自宅には多くの脅迫文や進入者があとを立たず、イギリス警察からワーナーブラザースへ上映を断念するよう申し入れがあった。家族にも危険が及びかねない状況に憂慮したキューブリックは、イギリス本国での公開を自ら幽閉したのだった。 この映画は、僕にとって映画の歴史上で、金字塔といえるくらい重要な映画だ。その過激すぎる内容は、暴力やセックスの場面が登場するため、一部批評家や観客からは毛嫌いされている傾向もあるが、それは「木をみて森を見ず」と同じことではないかと考えている。この映画の本質は、「体制主義による管理の脅威」にあることを読み取る必要がある。人間の本能というべき欲望を抑えるために、その人間を社会が人工的に洗脳し管理した場合、行き着くところはどうなるかという重要なテーマが隠されている。しかし、公開当時にイギリスの世論はキューブリックに厳しく、暴力を肯定する危険な人物と一方的に弾劾され、不穏な社会状況と相まみれてか、自宅には多くの脅迫文や進入者があとを立たず、イギリス警察からワーナーブラザースへ上映を断念するよう申し入れがあった。家族にも危険が及びかねない状況に憂慮したキューブリックは、イギリス本国での公開を自ら幽閉したのだった。
この映画は、1971年に製作されているが、近未来を描いた内容にもかかわらず、未だにその内容は色褪せていない。衣装、美術セット、音楽、セリフ、ポスターなど、すべてがポップアートとしての異彩を放っている。まず、「ミルクバー」にある裸婦のテーブルは、プロダクションデザイナーのジョン・バリーがヌードモデルにテーブルになる格好をしてみてくれと何度も試し、それをデザイン化しようとしたところ、そんなに多くのスタイルはみつからなかったそうだ。また、この作品の特徴は、ほとんどをロケ撮影しているという点である。当時、イギリス国内で撮影をするために、キューブリックとスタッフは、モダンアートの建築雑誌を丹念に調べ、未来社会を描くのにふさわしい場所を選んでいった。特に、老作家の屋敷は当時のモダン建築の最先端をいっているものだと容易に想像ができる。アレックスの住む集合住宅やキャットレディーの住む邸宅などもそうだ。
アレックスの役には、「ifもしも」で反体制の学生を演じたM・マクダウェルが抜擢されたが、オープニングの「不適な笑み」だけで、まさしく適役であったことが納得できると思う。この映画のキャスティングによって、この俳優の人生は決定づけられた不幸な例ではあるが、これ以後もまともな役はほとんど演じていない。「カリギュラ」などはそのいい例であろう。
低予算で短期間に撮影したこの作品は、長期撮影が常識になっているキューブリックにとってもそのフィルモグラフィーの中で特異な存在である。この映画では広角レンズを多様しており、左右がすこし歪む映像を敢えて効果的に使用している。
また、コマ落しやスローモーション、ズームからワイドへの多用、手持ちカメラによるぶれ、前進後退の移動撮影など、あらゆる手法が取り入れられている映画撮影の教科書にもなり得る映画だ。
『バリー・リンドン』(1975/Barry Lyndon)
 どうしても「ナポレオン」を撮りたかったキューブリックだが、資金面で目途が立たず、断念せざるを得なかった時期に、サッカレーの本を読んでいたキューブリックは、古典を撮ることに執念を燃やしていたことと重なり、ついに「バリー・リンドン」という「ナポレオン」を撮ることにした。 当時、キューブリックは、自分自身で本を1冊書けるほど、ナポレオンに関する膨大な文献や資料を熟読しており、その知識は、当時の生活様式を再現するのに大きな力となっている。この映画は、結果的に興行面で振るわなかったが、その反面、数多くの賞を受賞している。それは、撮影技術的な面や美術、音楽などの付加的なものへの評価であったにもかかわらず、いかに古典を再現してみせることは非常に丹念な研究と努力が必要であったかを、映画そのものへの賞賛する声は少なくなかった どうしても「ナポレオン」を撮りたかったキューブリックだが、資金面で目途が立たず、断念せざるを得なかった時期に、サッカレーの本を読んでいたキューブリックは、古典を撮ることに執念を燃やしていたことと重なり、ついに「バリー・リンドン」という「ナポレオン」を撮ることにした。 当時、キューブリックは、自分自身で本を1冊書けるほど、ナポレオンに関する膨大な文献や資料を熟読しており、その知識は、当時の生活様式を再現するのに大きな力となっている。この映画は、結果的に興行面で振るわなかったが、その反面、数多くの賞を受賞している。それは、撮影技術的な面や美術、音楽などの付加的なものへの評価であったにもかかわらず、いかに古典を再現してみせることは非常に丹念な研究と努力が必要であったかを、映画そのものへの賞賛する声は少なくなかった
写実的でシンメトリーな場面は、絵画的で、優雅で、ドキュメンタリー的でもあり、当時を暮す人々の息づかいや匂いまでが画面を通して感じることのできる芸術的な作品といえる。映画として一般的に致命傷扱いされる、非常に長い上映時間についても、いかにして、「ひとりの田舎者がふとしたきっかけで、成り上がり、詐欺行為をして貴族の仲間入りをしたところで、ついには拭いきれない野卑と自己の憐れみによって不遇の身になり、人生を終えたか」という人生を、淡々と描くには短かすぎることはあっても、決して長くは感じさせることはない。それでも、明らかに、キューブリックはこの映画を短縮するために、敢えてボイスオーバーを使用しているが、この効果は、突き放した視点というものを観客に意識させ、ラストの「ここに登場した人々はすべて墓の中」のクレジットを際立たせている。
この撮影中にアイルランドでのロケでは、IRAから脅迫を受け、一時撮影を中断したり、イギリスでは国宝級の建物や美術品を借りて撮影するため、細心の注意を払う必要があり、ストレスでじん麻疹ができ、この映画では、相当、神経をすり減らしてしまったキューブリックであった。興行的にはワーナーに制作費を回収させることができなかった唯一の作品である。
『シャイニング』(1980/The Shining)

自作で最もコマーシャル(商業的)な作品だと、のちにキューブリックは述べている。それもそのはず、彼は、前作の「バリー・リンドン」で興行的に振るわず、全面的な資金提供をしてくれるワーナーブラザースには、次回作では高収益をもたらせてやる必要があった。彼は、さまざまな小説や文献を読み漁り、いままで挑戦していないホラー映画を創造することに決めた。原作「ザ シャイニング」はホラー小説の第一人者スティーブン・キングだ。この執念深い男は、ことあるごとに「キューブリックの作品はひどすぎる。俺の小説をまったく無視している」とコメントしているが、しまいには自分でTV映画を製作している。そのビデオを鑑賞したが、ホテル自体が生き物のように描いており、超常現象に重きを置いた展開は、いわばオカルト映画に近く、映像や恐怖の点ではまったく比較にならない凡作だった。
キューブリックは女性脚本家のダイアン・ジョンソンと書いたシナリオは、霊がはびこるホテルにいることによって、ジャック・ニコルソンが狂気に変貌していく恐怖を、実に丹念に描いている。批評家によっては、もうすでにジャック・ニコルソンが狂っているように見えるとの意見もあったが、アル中で、元教師で、息子のダニーを脱臼させたことがある男が、やがて、あちら側のアジテーションによって、無意識のうちに家族を矯正しようという悪夢に取り付かれていく怖さがあった。
ある批評には、ダニーの持っている超能力(シャイニング)を、ホテルの死霊たちがそれを手に入れようとしてジャックを利用したと書いてあり、こういう解釈もあるのだと感心させられた。とても洗練された映像美学と、独特の冷たい雰囲気がたまらなく魅力的だ。何度観てもその都度、新しい発見があり、キューブリックが描く精神世界の深淵を垣間見ることのできるモダンなホラー映画である。
『フルメタル・ジャケット』(1987/Full Metal Jacket)
前作「シャイニング」から9年も待たされたが、ついに発表したのがベトナム戦争を題材にしたこの作品だった。アメリカがジョン・ウェインを主役とした自国の正義を前面に出した「戦意高揚映画」が主流を占めていた戦争映画というジャンルに、自己批判をしようとし始めたのが1980年代だった。特にペキンパーの「戦争のはらわた」が最初だといわれているが、続々とアメリカの自由というものに疑問を投げかけた作品が数多く登場した。「ディア・ハンター」「ハンバーガー・ヒル」「プラトーン」「カジュアリティーズ」「ランボー」「帰郷」などが挙げられる。しかし、その頂点と言われる「プラトーン」は批評家からは絶賛されたが、本当の戦争の本質を描いたわけではなく、どこかヒューマニズムという調 味料がふりかけられていた。キューブリックの「フルメタル・ジャケット」は、戦争を否定や肯定もしていないが、戦争とは人間が殺人マシーンに変えられ、人格あるいは自己というものを徹底的に抹殺されてこそ成り立つという本質を、いかにもクールな目で見据えているところにこそテーマがある。微笑みデブは、殺人マシーンとしていよいよ本稼動するべき矢先に、HAL2000と同じく狂いはじめ、ついには暴発してしまう。戦争という狂気じみた状況下では、機械化した人間は、その目的を正確にやり遂げることのみ存在価値があり、それ以外のことをすれば、規格品から無用とされるのだ。
また、ジョーカーたちが最強の戦闘マシーンとして前線に送られても、たったひとりの女性狙撃兵(人間)にいたぶられるように右往左往し、屈強な男たちが仕留めたのは小柄なベトコンだったと愕然とする、何とも皮肉なシーンがラストを飾る。なお、この映画の音楽は娘のアビゲイル・ミード(ヴィヴィアン・キューブリック)が担当している。 味料がふりかけられていた。キューブリックの「フルメタル・ジャケット」は、戦争を否定や肯定もしていないが、戦争とは人間が殺人マシーンに変えられ、人格あるいは自己というものを徹底的に抹殺されてこそ成り立つという本質を、いかにもクールな目で見据えているところにこそテーマがある。微笑みデブは、殺人マシーンとしていよいよ本稼動するべき矢先に、HAL2000と同じく狂いはじめ、ついには暴発してしまう。戦争という狂気じみた状況下では、機械化した人間は、その目的を正確にやり遂げることのみ存在価値があり、それ以外のことをすれば、規格品から無用とされるのだ。
また、ジョーカーたちが最強の戦闘マシーンとして前線に送られても、たったひとりの女性狙撃兵(人間)にいたぶられるように右往左往し、屈強な男たちが仕留めたのは小柄なベトコンだったと愕然とする、何とも皮肉なシーンがラストを飾る。なお、この映画の音楽は娘のアビゲイル・ミード(ヴィヴィアン・キューブリック)が担当している。
『アイズ ワイド シャット』(1999/Eyes Wide Shut)
 ダゲレオ出版「キューブリック」を読み直すと、キューブリックが「時計じかけのオレンジ」を撮ろうとしている1970年当時に、A・シュニッツラー原作の「トラウマノベル」をもとに「ラプソディー/夢の小説」という企画が確かにあったのを確認できる。たぶん、この作品は念願の映像化だったのではないかと想像できる。 私は前作の「フルメタル・ジャケット」から待ちに待たされ、ついに、7月31日の初日に遺作となったこの映画観てきた。この作品はまさしくキューブリックの傑作であり、また集大成のように感じた。過去の作品群のイメージがあらゆるところで引用され、私たちに最後のメッセージを投げかけているような映画だった。映画の巨匠といわれた人たちは、老いると精神世界に目を向け、パワーの衰えは隠しきれないものだが、キューブリックは若いときから精神世界には着目していたことになり、この映画の映像は本当に70歳とは思えないほどパワフルである。キューブリックはこの作品で燃え尽きたのだろうか? もちろん賛否両論はキューブリックも承知の上のことであっただろう。しかし、人間の性をこれほどまじめに描いているとは思わなかった。そして、この映画のテーマが、オーストリアの心理学者「ジークムント・フロイト」がその著書「精神分析学入門」で唱えた、人間の<無意識>であると私は思う。 ダゲレオ出版「キューブリック」を読み直すと、キューブリックが「時計じかけのオレンジ」を撮ろうとしている1970年当時に、A・シュニッツラー原作の「トラウマノベル」をもとに「ラプソディー/夢の小説」という企画が確かにあったのを確認できる。たぶん、この作品は念願の映像化だったのではないかと想像できる。 私は前作の「フルメタル・ジャケット」から待ちに待たされ、ついに、7月31日の初日に遺作となったこの映画観てきた。この作品はまさしくキューブリックの傑作であり、また集大成のように感じた。過去の作品群のイメージがあらゆるところで引用され、私たちに最後のメッセージを投げかけているような映画だった。映画の巨匠といわれた人たちは、老いると精神世界に目を向け、パワーの衰えは隠しきれないものだが、キューブリックは若いときから精神世界には着目していたことになり、この映画の映像は本当に70歳とは思えないほどパワフルである。キューブリックはこの作品で燃え尽きたのだろうか? もちろん賛否両論はキューブリックも承知の上のことであっただろう。しかし、人間の性をこれほどまじめに描いているとは思わなかった。そして、この映画のテーマが、オーストリアの心理学者「ジークムント・フロイト」がその著書「精神分析学入門」で唱えた、人間の<無意識>であると私は思う。
人間の性への欲望が抑圧されると<無意識>という領域にて達成しようとするのが「夢」であると唱えたフロイトの説を映像にした映画なのである。<意識>では「私は絶対浮気なんかしない」と思っていても、本人が自覚していない能の<無意識>では「めくるめくハーレムのようなセックス」の夢をみるのは、抑圧された欲望の具現化なのだ。つまり、冷ややかな目でキューブリックが好んで描いてきた「抑圧された人間の行動」を、この「アイズ
ワイド シャット」でも取り上げているのだ。
さまざまな、社会的抑圧やモラルに囚われた人間はまさに<仮面>を被って生きているが、その仮面の下<無意識>では、その欲望が嵐のように渦巻いていることを映像で我々に見せてくれたのだと感じる。ただ、ほとんどの人は、ビル・ハーフォードのように抑圧された願望を実現できずに生きていて、アリスのように「夢」の中で願望を達成しており、キューブリックは「アイズ
ワイド シャット」という遺作をもって、人間のもつ心理の深淵をかいま見せて、これ以上覗いては危険だよと、そっとふたを閉じてくれた(アイズ ワイド シャット)のではなかろうか。
もう一方で、この映画の視点は、ビルという一般的な男性を中心として展開されているが、実はアリスという非常に二面性をもった女性からの視点も描かれており、昼は貞淑な妻で夜は娼婦になりえるという女性の欲望の内面をストレートに表現しているところに、キューブリックの意図が見えてくる。 遺作なので、もうこれでキューブリックの新作は永久に鑑賞できないと思うとエンドタイトルのクレジットをみつめながら、僕は感無量だった。そして、映画が終わり、最後のクレジットで「キューブリックありがとう。そして、さようなら」と心の中で別れを言った。
最後に我田引水ではあるけれど、ワンシーンに「黒のVWゴルフ」が映っていたこと、そして、T・クルーズが勤務する病院のオフィスにあったパソコンが「Macパフォーマ」だったことが、まるで僕に「私の映画を心から敬愛してくれてありがとう」とキューブリックが語りかけてきたようだった。
|